ワーキングホリデーの年金・税金・保険

ワーキングホリデーの準備というと、ビザの取得や航空券の手配、住まい探しなど、どうしても"渡航後の生活"に意識が向きがちですよね。でも実は、出発前にもうひとつ大切なのが、「お金と制度に関すること」。特に年金・保険・税金といった"国とのつながり"をどう扱うかは、ワーホリをスムーズに進めるために欠かせないポイントです。
たとえば、
日本の年金はワーホリ中でも支払い義務があるのか?住民税や所得税はどうなるの?健康保険は抜けるべき?さらには、渡航先で働くと自動的に加入する制度、たとえばオーストラリアの「スーパーアニュエーション(退職年金制度)」や現地の課税システムについても、事前に知っておくことで「知らなかった!」を防げます。そして帰国後、こうした制度が自分の将来にどんな影響を与えるのかも、あらかじめ理解しておけば安心です。
この記事では、ワーホリ前に知っておきたい「年金」「保険」「税金」に関する基本情報を、わかりやすく整理してお伝えします。不安や疑問をスッキリ解消して、安心して海外に飛び立てるよう、ぜひチェックしてみてください。
経験豊富なカウンセラーに分からないことを聞いてみよう!
- 1. ワーホリに行く前に知っておくべき「年金」のこと
- 1-1. 日本の年金はどうなる?加入義務はある?
- 1-2. 年金の免除・猶予制度について
- 1-3. 海外で払う年金とは?(例:オーストラリアのスーパーアニュエーション)
- 1-4. 帰国後の年金への影響は?
- 2. ワーキングホリデー中の「健康保険」はどうなる?
- 3. ワーキングホリデー中の「税金」はどうなる?
- 3-1. 日本での住民税・所得税は?住民票はどうする?
- 3-2. 現地での税金(例:タックスファイルナンバー、ワーホリ税率)
- 3-3. タックスリターン(確定申告)の必要性と方法
- 3-4. 帰国後の課税対象になるケース
- 4. 帰国後にやるべき手続きまとめ
- 5. 国別の年金・保険・税金の違い
- 6. よくある質問(FAQ)
- 7. まとめ
1. ワーホリに行く前に知っておくべき「年金」のこと
日本の年金はどうなる?加入義務はある?
日本国民は20歳以上になると、原則として「国民年金(基礎年金)」に加入する義務があります。これは海外に住んでいても例外ではなく、ワーキングホリデー中であっても年金加入義務は継続しています。
ただし、実際に支払いを続けるか、免除・猶予制度を利用するかは自分で選ぶことができます。放置して未納になると、将来の年金受給に影響が出たり、障害年金の受給対象から外れてしまう可能性があるため注意が必要です。
年金の免除・猶予制度について
ワーホリで長期的に日本を離れる場合は、「国民年金保険料の免除」または「納付猶予制度」を申請することができます。
免除制度の特徴
- 一定の所得以下であれば全額〜一部免除が可能
- 将来の年金額には影響が出るが、一部は加算される
納付猶予制度の特徴
- 50歳未満の人が対象
- 後から追納すれば将来の年金額に反映される
手続きのタイミングと方法
- 渡航前に「住民票のある自治体」で申請が必要
- ワーホリビザの写しや渡航予定の確認書類が必要
しっかり手続きをしておけば、未納扱いにはならず、将来の年金への影響を最小限に抑えることができます。
海外で払う年金とは?(代表的なワーホリ渡航先の制度)
ワーキングホリデー中に現地で働くと、その国の法律に従って年金制度に加入するケースがあります。
ここでは、主要なワーホリ対象国における年金制度の特徴を、「自動加入の有無」「ワーホリも対象になるか」「帰国時に払い戻せるか」の3点に注目して紹介します。
オーストラリア:Superannuation(スーパーアニュエーション)
- 自動加入?→✅Yes(雇用主が義務として積み立て)
- ワーホリも対象?→✅Yes(一定額以上の収入がある場合)
- 払い戻し可能?→✅Yes(DASP制度)
特徴
- 雇用主が給与の11%を積立(2025年現在)
- 本人は負担なし、DASP申請で帰国後に受け取れる
- 払い戻しには税金(35〜65%程度)が差し引かれることもある
ニュージーランド:KiwiSaver(キウィセーバー)
- 自動加入?→❌No(希望者のみ)
- ワーホリも対象?→⭕ 希望すれば加入可能
- 払い戻し可能?→❌No 基本的に不可(一部条件下で可)
特徴
- 加入は任意、自己拠出+雇用主拠出+政府の補助あり
- 長期的な制度で、原則65歳まで引き出せない
カナダ:Canada Pension Plan(CPP)
- 自動加入?→✅Yes(雇用主・従業員が拠出)
- ワーホリも対象?→✅Yes(収入がある場合)
- 払い戻し可能?→❌原則不可
特徴
- 雇用主と従業員が折半で拠出(約11%)
- 将来カナダで年金を受け取る資格につながる
- 日本との社会保障協定なし → 払い損になることも
ドイツ:法定年金制度(Gesetzliche Rentenversicherung)
- 自動加入?→✅Yes(原則すべての労働者)
- ワーホリも対象?→✅Yes(一定時間以上の労働で対象)
- 払い戻し可能?→✅条件付きで可能
特徴
- 最低24か月の加入後、帰国後に払い戻し申請可(約18か月後)
- 返金率は拠出額の一部(100%ではない)
- 申請には書類や時間がかかる
イギリス:National Insurance(NI)
- 自動加入?→✅Yes(雇用されれば自動的に)
- ワーホリも対象?→✅Yes(一定収入超えると対象)
- 払い戻し可能?→❌不可
特徴
- 所得に応じて保険料を支払い
- NHS(国民保健サービス)などの財源にも使われる
- 将来年金の対象になるが、短期滞在では実質意味がないことも
| 国 | 自動加入 | ワーホリ対象 | 払い戻し可能 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| オーストラリア | ● | ● | ● (DASP) | 払い戻し手続きは必須、税金に注意 |
| ニュージーランド | ✖ (任意) | ● (任意加入) | ✖ (原則) | 長期居住者向け、短期なら加入不要 |
| カナダ | ● | ● | ✖ | 払い戻し不可、日本と協定なし |
| ドイツ | ● | ● | ● (条件付き) | 一定条件で返金可能、手続きに時間がかかる | イギリス | ● | ● | ✖ | 医療にも使われる制度、返金なし |
帰国後の年金への影響は?
ワーホリから帰国した後の年金にも注意が必要です。免除・猶予申請をしていた場合は、帰国後にすぐ「納付再開」の手続きを行いましょう。何もしないままだと、未納期間が延びて将来の年金額が減ってしまう可能性があります。
また、免除や猶予を利用していた期間は、あとから追納することで将来の年金に反映されます。帰国後の収入状況に応じて、追納を検討するのもひとつの方法です。
カウンセラーに相談してみよう!
2. ワーキングホリデー中の「健康保険」はどうなる?

日本の健康保険は継続?脱退?
出国前に住民票を残すかどうかで異なる
住民票を抜いた場合は、原則として国民健康保険を脱退する手続きが必要になります。日本では、住民票のある市区町村において健康保険の加入義務が発生するため、海外に長期間滞在する目的で住民票を抜いた場合、その対象から外れることになります。これにより、国民健康保険料の支払い義務はなくなりますが、当然ながら日本国内での医療サービスを受けることもできなくなります。
一方で、住民票を残したまま渡航する場合は、引き続き日本の住民として扱われるため、国民健康保険への加入義務も継続されます。つまり、日本に住んでいない期間であっても、毎月の保険料を支払い続ける必要があるということです。そのため、留学やワーキングホリデーなどで長期的に海外に滞在する場合は、住民票を抜いて健康保険を脱退する方が一般的といえるでしょう。
ただし、出国期間が3か月未満の短期の場合や、帰国後すぐに保険の利用を再開したいと考えている方は、住民票を残して保険を継続するという選択肢もあります。それぞれのケースによって最適な判断が異なりますので、出発前にしっかりと計画を立て、市区町村の窓口で確認しておくことをおすすめします。
海外の医療保険は加入すべき?
海外の医療保険には必ず加入すべき
ワーキングホリデーで海外に渡航する場合、海外の医療保険には必ず加入すべきです。その理由は大きく分けて2つあります。ひとつは、多くの国でワーキングホリデービザの申請時に保険加入が義務付けられているという点。たとえばオーストラリアやニュージーランドでは、ビザ条件として「滞在中の全期間にわたり適切な医療保険に加入していること」が求められることがあります。
もうひとつの理由は、現地で病気やケガをした場合にかかる医療費が非常に高額であることです。日本と異なり、国民皆保険制度がない国も多く、救急搬送・入院・手術などが発生した場合には、数十万円〜数百万円単位の費用がかかることも珍しくありません。このような緊急事態に備えて、事前に海外保険に加入しておくことは、自分の身を守るうえでも大切な準備といえるでしょう。
また、海外旅行保険には金銭面の補償だけでなく、「キャッシュレス診療が可能な提携病院での治療」「日本語対応のサポートデスク」などの手厚いサービスが含まれていることも多く、特に語学力に自信のない方や初めての海外生活を送る方にとっては、精神的な安心感も大きなメリットです。 ワーホリ中の体調不良や事故は、誰にでも起こりうる可能性があります。万が一の事態に備えて、信頼できる海外保険に加入し、安心してワーキングホリデー生活をスタートできるよう準備を整えましょう。
クレジットカード付帯保険との違いと注意点
クレジットカード付帯保険だけに頼るのは非常にリスクが高い
ワーキングホリデーに出発する前に、「クレジットカードに海外旅行保険が付いているから、それで十分では?」と考える方も少なくありません。しかし、クレジットカード付帯の保険だけではカバーしきれない点が多く、ワーホリのような長期滞在には不十分であることがほとんどです。
まず、補償期間についてですが、多くのクレジットカードに付帯している保険は最大でも90日程度となっており、それを超える長期滞在には対応していません。一方、海外旅行保険(任意加入)は、1年間の補償が可能で、ワーホリ滞在期間をしっかりカバーできます。
また、補償内容にも大きな違いがあります。クレジットカード付帯保険では、治療費の補償額が少額に設定されていることが多く、入院や手術といった大きな医療費には対応しきれないケースがあります。一方、任意で加入する海外旅行保険では、入院費・手術費・賠償責任・盗難被害なども含めた、より広範囲で手厚い補償が用意されています。
さらに、現地でのサポート体制も異なります。クレジットカード付帯保険は、基本的に現地語や英語での対応が主流で、日本語でのサポートが受けられないことが多いです。それに対して、海外旅行保険では、日本語での24時間サポートデスクが用意されているものが多く、慣れない海外でも安心して相談できる体制が整っています。
おすすめの海外旅行保険・ワーホリ専用保険は?
目的・渡航先・期間に合わせて、補償内容と金額をしっかり比較
1. 渡航先のビザ条件を確認
国によっては、保険の種類や補償内容に制限がある場合があります。たとえば、オーストラリアでは「OSHC(海外留学生健康保険)」の加入が必要なケースもあるため、まずは渡航先のワーホリビザ条件をしっかり確認しましょう。
2. 補償内容は「医療費」「賠償責任」「携行品損害」などをチェック
特に重要なのが医療費の補償額と対応範囲です。現地での入院・手術・救急搬送にも対応しているかを確認しましょう。加えて、万が一人にケガをさせてしまった場合に備える「賠償責任」や、スマホやPCなどの破損・盗難に備える「携行品損害」も要チェックです。
3. サポート体制の充実度で選ぶ
日本語のサポートデスクがあるか、キャッシュレス診療に対応している病院があるかは安心して生活するうえで非常に大切なポイント。トラブル時にすぐに連絡できる窓口がある保険を選びましょう。
4. 渡航期間に合ったプランかどうか
ワーホリは1年間の長期滞在になるため、保険も「長期契約が可能なプラン」を選ぶことが基本です。短期旅行用の保険では期間が足りず、渡航後にトラブルが発生する可能性があるため注意が必要です。
5. 自分にとっての「安心」のバランスで選ぶ
補償範囲が広いほど保険料は高くなりますが、「どこまでを自分でリスク許容できるか」を考えながら、予算と安心感のバランスを取りましょう。たとえば、歯科治療や精神的ケアも含まれているプランもあり、希望に応じて選ぶことが可能です。
保健会社の選択
AIG損保|ワーキングホリデー保険:実績豊富/サポート体制◎
特徴
- ワーホリ・長期滞在者向けに専用設計されたプランあり。
- 緊急時の日本語サポートデスクが24時間365日対応。
- 医療通訳手配やキャッシュレス診療(提携病院で可能)あり。
メリット
- 日本出発前の申込&万が一のトラブル時の安心感が大きい。
- 緊急時の日本語サポートデスクが24時間365日対応。
- 提携先の医療機関が多く、海外でもスムーズに対応可。
ジェイアイ傷害火災(t@biho・たびほ):オンライン契約可・自由設計が可能
特徴
- インターネットで簡単に見積もり~契約まで完結。
- 補償内容を自分でカスタマイズ可能(例:疾病治療費を厚く、携行品は最低限など)。
メリット
- 費用を抑えたい人・保険は自分に合うように選びたい人向け。
- 1年間のワーホリや留学にも対応したプランあり。
東京海上日動|海外旅行保険:大手の安心感+キャッシュレス医療対応の病院多数
特徴
- 世界中に提携病院ネットワークを持ち、キャッシュレス診療が受けられる。費を厚く、携行品は最低限など)。
- サポートセンターの質も高く、トラブル時の対応が非常にスムーズ。
メリット
- 信頼重視、トラブル時の手厚い対応を期待したい人向け。
- 査定や保険金請求も早いと評価が高い。
ワーホリ向けの保険について聞いてみよう!
3. ワーキングホリデー中の「税金」はどうなる?

ワーキングホリデーに行くとき、意外と見落としがちなのが「税金」のこと。 日本の住民税や所得税、渡航先の税金、さらには帰国後の申告義務など、正しく知っておくことでトラブルを防げます。
この記事では、ワーホリ前・滞在中・帰国後に関わる税金の基礎知識を、わかりやすく解説します。
日本での住民税・所得税は?住民票はどうする?
ワーホリに行っても住民税はかかる?
日本の住民税は「1月1日時点で住民票があるか」で課税されます。 つまり、ワーホリ中でも1月1日に日本に住民票があると、その年の住民税が課されるのです。
対策:出発前に「住民票を海外転出」しよう
出国前に市区町村役場で「海外転出届」を提出すると、住民票が抜け、翌年の住民税が免除される可能性があります。所得税についても、給与所得がなければ基本的に課税されません。
ポイント!
ワーキングホリデー前に転出届を出すことで、無駄な税金を防げます!
現地での税金(例:タックスファイルナンバー、ワーホリ税率)
ワーキングホリデーで現地就労をするには、オーストラリア・ニュージーランド・カナダいずれの国でも、働く前に納税者番号の取得が必須です。これがないと雇用主が法的に給料を支払えない場合や、不利な高税率で源泉徴収されてしまうことがあるため、現地到着後はできるだけ早く申請しましょう。
タックスファイルナンバー(TFN)とは?
オーストラリアやニュージーランドなどでは、働く前に「納税者番号」の取得が必要です。これがないと、高い税率で源泉徴収されることがあるので注意です。
- オーストラリア:TFN(Tax File Number)
- ニュージーランド:IRDナンバー
- カナダ:SIN(Social Insurance Number)
ワーキングホリデー用の税率とは?
- オーストラリア:$0〜$45,000まで15%課税(ワーホリタックス)
(※オーストラリアなどでは「ワーホリビザ保有者用の特別な税率」があります。) - ニュージーランド:通常の所得税(10.5%〜)
- カナダ:累進課税+州税が上乗せ
タックスリターン(確定申告)の必要性と方法
ワーキングホリデー中に働いて収入を得ると、給料から所得税が源泉徴収されます。しかし、実際の収入や課税額に応じて税金を払いすぎているケースも少なくありません。
その場合に行うのが「タックスリターン(Tax Return)」と呼ばれる確定申告による税金の還付申請です。特にオーストラリア、ニュージーランド、カナダでは、ワーホリ終了時に申告することで、税金が一部または全額戻ってくる可能性があります。
申請方法の例(オーストラリア)
- 申請方法:オンラインでATO(オーストラリア税務局)にアクセスして申告
- 申請時期:ワーホリビザの有効期限が切れたあとでも、帰国後に申請OK
- 必要なもの:
PAYG(源泉徴収票)...働いた会社からもらえます
TFN(タックスファイルナンバー)...納税者番号
銀行口座情報...還付金を受け取るために必要
代行サービスもある
語学学校や現地エージェントを通じて、タックスリターン代行サービスを紹介してもらえることも。
帰国後の課税対象になるケース
日本に再び住民票を戻すと、翌年から住民税が再課税
日本に帰国して住民票を戻すと、翌年から住民税の支払い義務が発生。 ワーホリ中の収入は、基本的に日本の所得税・住民税には含まれません。
例外:日本の口座に収入を受け取っていた場合
海外で得た収入でも、日本の銀行に直接送金していたり、投資収益などがあると申告対象になる場合も。 不安な場合は、税務署や専門家への相談がおすすめです。
4. 帰国後にやるべき手続きまとめ
ワーキングホリデーを終えて日本に帰国したら、「やるべき手続き」がいくつかあります。特に、年金の再加入や追納、税金関係、住民票の再登録、保険の切り替えなどは、早めに対応しておかないと損をする可能性も。帰国後の必要な手続きを見てみましょう。
年金の再加入・追納について
帰国後はまず、日本の国民年金への再加入が必要です。ワーホリ中に住民票を海外転出していた方は、年金の納付義務がなかったため、未納期間が発生している可能性があります。 この未納期間は、帰国後に「追納(ついのう)」という形であとから支払うことも可能です。将来の年金受給額に関わるため、将来のことを見据えて検討しておくと安心です。
- 申請場所:お住まいの市区町村の役所
- 追納できる期間:最大10年間までさかのぼって支払い可能
税金の手続き・住民票の再登録
ワーホリ出発時に「海外転出届」を提出していた方は、帰国後に住民票の再登録が必要になります。これをしないと、国民健康保険や年金などの行政サービスが受けられない場合があります。
また、住民票を再登録することで、翌年の住民税や所得税の対象にもなるため、収入の有無に応じて税務署での相談もおすすめです。
- 手続き場所:帰国後14日以内に住む予定の市区町村役場
- 必要なもの:パスポート、マイナンバーカード(または通知カード)
保険の切り替え(国保・社会保険など)
日本に帰国して働き始める場合、会社員なら社会保険に加入することになりますが、就職前やフリーランスの場合は、国民健康保険(国保)への加入が必要です。
住民票を再登録したあと、速やかに保険の切り替え手続きを行いましょう。保険が未加入のままだと、医療費が全額自己負担になるリスクもあります。
- 国保加入は住民票登録と同時に可能
- 就職後は会社側が社会保険の手続きをしてくれる
ワーホリに行く前の手続きについて聞いてみよう!
5. 国別の年金・保険・税金の違い
ワーキングホリデー中は、国によって税金・年金・保険の制度が大きく異なります。滞在前にチェックしておくことで、損やトラブルを防ぐことができます。以下、各国の税金・年金・保険になります。
オーストラリア
- 税金:ワーホリ税制あり。年収$45,000までは15%課税(TFN登録必須)
- 年金(Superannuation):雇用主が拠出。帰国時に払い戻し申請可能(DASP)
- 保険:海外旅行保険に加入が基本(学生はOSHC加入義務あり)
カナダ
- 税金:連邦税+州税の累進課税、SINの取得が必要
- 年金:一時滞在者には基本関係なし
- 保険:私費保険に加入。一部の州では州保険に加入可能
ニュージーランド
- 税金:IRDナンバーで10.5%〜の累進課税
- 年金:長期居住者向け(NZ Super)→ワーホリには無関係
- 保険:Uni-Careなどの民間保険加入が一般的
イギリス
- 税金:年収£12,570以下なら非課税。国民保険番号(NIN)取得が必要
- 年金:一時滞在者は基本的に対象外
- 保険:IHS(移民医療サーチャージ)支払いでNHS利用可
アイルランド
- 税金:PPSナンバー取得が必須。年間€16,500まで非課税(2025年時点)
- 年金:公的年金制度はあるが、ワーホリの短期滞在者には基本的に無関係
- 保険:現地の公的医療制度(HSE)は一部利用可能だが、基本は海外旅行保険加入が安心
※HSEの医療サービスは無料〜低額だが、対象や条件が限定的
6. よくある質問(FAQ)
Q1: ワーホリ中でも年金払わないと将来困る?
<支払わなくてもOKだが「将来の年金額」が減る可能性あり!>
ワーキングホリデー前に海外転出届を提出すれば、国民年金の支払い義務は免除されます。 ただしその間の期間は、将来の年金受給資格の対象外になります。
<対処法:帰国後に「追納」が可能>
免除されていた期間の保険料は、最大10年まで遡って追納することが可能。 将来の年金額を確保したい方は、追納も視野に入れておくと安心です。
Q2:住民票を抜くメリット・デメリットは?
<メリット>
・住民税・国民健康保険・国民年金の支払いが不要になる
・無駄な支出を抑えられる
・長期滞在の場合、課税対象から外れるのが最大の利点
<デメリット>
・マイナンバーカードが一時的に使えなくなる
・日本国内での行政手続きが制限される
例:運転免許証更新、マイナポイントの利用など
日本の健康保険証が使えなくなる
<注意点>
住民税は「1月1日時点で住民票があるかどうか」で課税されるため、年をまたぐ前に転出届を出すのがベストタイミングです。
Q3:海外で働いた収入は日本で申告必要?
<基本は不要。ただし「居住者か非居住者か」で異なる>
ワーキングホリデーで海外転出届を出している=非居住者であれば、日本での確定申告義務は原則ありません。
ただし、以下のケースでは日本でも申告が必要になる可能性あり:
・海外での収入を日本の銀行に送金した場合
・日本に住民票を残したまま出国した場合(=居住者扱い)
・日本の企業からの報酬など、日本国内での所得がある場合
<ポイント>
・「海外転出届」で非居住者扱いにしておくのが最もシンプル
・帰国後、日本に収入を申告する必要があるか不安な場合は、税務署に相談を
ワーキングホリデーについて詳しく知る!
ワーキングホリデー総合案内
- ワーホリについて知ろう!ワーキングホリデーについて
- 退職して海外に行くメリット社会人のワーホリについて
- 海外で働く経験を積む大学生のワーホリについて
- 学ぶ・働く・旅行するワーキングホリデーで何ができる?
- 出発までにやっておくことワーキングホリデーの準備
- 現地で楽しく過ごそう!ワーキングホリデーの現地生活ガイド
- 国毎に比較してみようワーキングホリデーの国別比較チャート
- ワーキングの期間はどれくらい?ワーキングホリデーの期間
- ワーホリにいくらかかるの?ワーキングホリデーの費用
- ワーホリ体験談半年で150万円稼いだインターン体験談
- どんなサポートが受けられるの?サポートプログラムのご案内
- お電話でのご相談
- お急ぎの方はお電話にてお問い合わせください。
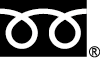 0120-945-504
0120-945-504
留学について知ろう!
成功する留学だからできること

カウンセラーは留学経験者なので、気兼ねなくご相談いただけます。
豊富な経験と知識で、一人ひとりに合った留学プランをご提案します。
▼ご質問やご不明点はお気軽にご相談ください!
▼留学デスクで個別相談する日程を予約しよう
全国どこからでもオンラインでご相談いただけます!






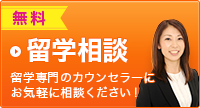

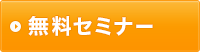

こんな点にも注意!
海外での年金払い戻し(例:オーストラリア)には税金がかかる場合あり、日本での課税対象になることもあるため、確定申告が必要になるケースも。