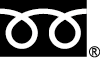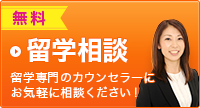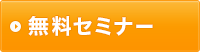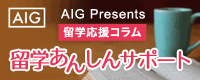人間の祖先はサルと考えられています。約35万年前に地球上に出現したネアンデルタール人が、最古のヒト属の一種と考えられています。1859年にチャールズ・ダーウィンが『種の起源』を著したのをきっかけに、動物の進化の研究が盛んに行われるようになりました。彼が進化論のヒントを得たのはガラパゴス諸島です。

ダーウィンはイギリス海軍の測量船ビーグル号で航海に出て、1835年9月15日から1ケ月余りの日々をガラパゴスの島で暮らしました。当時のガラパゴス諸島は囚人の流刑地でした。島を管理する総督からダーウィンは、ガラパゴスの島ごとに異なる種類のゾウガメが生息していることを知らされました。イグアナ、フィンチ、マネシツグミなども島によって固有の特徴があることに気づき、生物の種の進化や分化の発想が産み出されたのです。

現在ガラパゴス諸島で最も多くの人々が暮らすサンタ・クルス島に、チャールズ・ダーウィン研究所が設立されました。ガラパゴスの生態系の保全や調査のための施設ですが、遊歩道を歩きながら周辺の島々から集まられたゾウガメの飼育場を自由に見学することができます。子ガメの飼養場では故郷の島や孵化した年度によって分けられ、大切に飼育されています。エキシビション・センターではゾウガメの甲羅や体形の違いをパネルや実物標本で紹介しています。




ゾウガ甲羅の背中側の形から、ドーム型と鞍型の2種類に大別されます。進化の過程で草に覆われた島に暮らすゾウガメは、首を上げる必要がないため丸いドーム型となるのです。下草が少なく頭上の草をエサとせざるをえない島のゾウガメは、首が持ち上げやすくなるように鞍型の甲羅に進化したと考えられています。

サンタ・クルス島西部の高原地帯は雨が多く、ブラック・マングローブやスカレシアなどの木々が育ち、地面には一年を通してシダやスゲなどの草が繁茂しています。ゆるやかな起伏の丘には湿地も豊富なため、数多くのドーム型のゾウガメが暮らしています。エル・チャトと呼ばれるエリアはゾウガメの保護区となっています。野生ではあっても天敵を知らず人間を恐れることがないため、気がつくとゾウガメに囲まれてしまっていることもあります。




ガラパゴスのゾウガメは世界最大級のリクガメで、全長150センチ、体重250キロの巨体になるまでに育ち、寿命は200年を超えることもあります。かつては島やエリアによって15種類に分類されていましたが、4種が絶滅し現在は11亜種、約2万頭が島々で生活しています。ガラパゴスはスペイン語で馬の鞍を意味します。馬の鞍のような甲羅をもつゾウガメが数多く見られたことから諸島の名前がつけられたのです。ガラパゴス諸島は、1978年にユネスコ世界遺産の第1号として登録されました。

【データ】
施設名:チャールズ・ダーウィン研究所 Charles Darwin Foundation
住所:Puerto Ayora, Santa Cruz Island, Galapagos, Ecuador
Tel:(05)252-6146
URL:http://www.darwinfoundation.org/en/
開館時間:早朝〜夕方
休み:無休