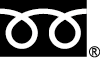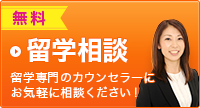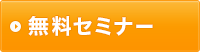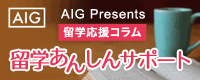日本は明治維新以来、大量に欧米諸国から技術や文化が流れ込んできました。未知のものを積極的に取り入れることによって急速に近代化が進みましたが、海外から一方的に技術や文化を取り入れたわけではありません。日本からも様々なものが海を越えて行きました。中でも浮世絵は、19世紀末のヨーロッパに新しい表現を築くきっかけとなりました。ジャポニスムの影響からアール・ヌーヴォーの表現様式が産まれたのです。芸術の都パリに留まらず、ナンシーでは多くの作家が新たな創作に励みました。市内の美術館では、ナンシー派と呼ばれる作家の作品が数多く展示してあります。

ドイツとの国境に近いナンシーへは、パリからフランス国鉄の高速鉄道TGVを利用すれば1時間半前後です。駅舎に隣接すスタニスラス門からスタニスラス通りを北東に約1キロ歩くと、大きな広場に吸い込まれていきます。


スタニスラス広場は、ブルボン朝第4代国王ルイ15世の義父ロレーヌ公スタニスラスが、エマニュエル・エレに設計を託し1755年に完成させました。創設当時は広場の中央には国王の像が設置されていましたが、フランス革命のときに破壊され1831年にスタニスラスに姿を変えました。像を中心として縦横約106メートル、124メートルの面には市庁舎やナンシー美術館が建っています。


車が侵入してこない歩行者のための広場は、いつも大勢の人々で混みあっていますが、観光客のお目当ては、その空間にはないようです。魅力は敷地内ではなく、これを取り囲む周囲に鏤められているのです。四方八方に設けられた出入口が極めて特徴的なのです。金具師ジャン・ラムールは、6つの鉄柵を外周にデザインしました。いずれにもロココ様式が活かされ、門の構造がもつ上下のラインに繊細な曲線が優雅に絡み合っています。金色と黒色の配色も印象的で華やかさが滲み出てきます。


広場の北側に設けられているのは細い金属細工による門ではなく、パリのエトワール広場を思い起こしそうな凱旋門です。見るからに頑丈そうな石造りのアーチ門を潜ると、さらに南北に細長い広場が続きます。カリエール広場は18世紀に整備されましたが、16世紀にはここで馬上槍競技が行われていたと伝わります。

ナンシーは11世紀頃からロレーヌ公国の首都として発展しました。街の景観を整えたスタニスラスが執務をとったロレーヌ公宮殿は、カリエール広場の北に置かれました。現在はロレーヌ歴史博物館として公開されています。博物館の東に広がるペピニエール公園には緑に溢れ、カテドラルの尖塔も見ることができます。



ナンシーのスタニスラス広場、カリエール広場は、アリアンス広場とともに1983年にユネスコの世界遺産に登録されました。
【データ】
施設名 : スタニスラス広場 Place Stanislas
住所 : Place Stanislas, 54000 Nancy
アクセス : ナンシー駅から北東に徒歩約10分