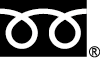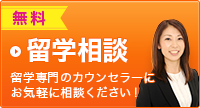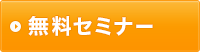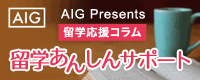日本の総人口の1割以上が暮らす東京は政治、経済の中心ですが、一極集中による問題を抱えています。1992年に国会等の移転に関する法律が成立しました。様々な機関の移動が検討されていますが、実行例はまだありません。国政を担う施設の移動は容易なことではないのでしょう。ところが、1991年にチリの国会の移転が行われました。議場は首都のサンティアゴからバルパライソに移されたのです。

バルパライソは南北に細く長いチリのほぼ真ん中で、太平洋に面する港町です。サンティアゴから西に約120キロで、ハイウエイバスを使えば2時間足らずのアクセスです。バスターミナルの正面には、真新しい国会議事堂が建っています。

バルパライソの市街地は、湾に沿って東西に細長く延びています。僅かな海辺の平地に向かって、丘陵が折り重なるように迫っています。1536年にスペインからやって来たディエゴ・デ・アルマグロが、天国のような谷を連想したことからバルパライソと命名されました。パナマ運河が開設される前には、マゼラン海峡を航行する多くの船が次々にバルパライソの港に入港したために急速な発展を遂げました。現在でもサンティアゴの外港としてチリで最も重要な役割を果たしています。

人口が増えても平らな土地は南北の方向に数百メートル程度しかありません。民家は丘の斜面や上にも建てられるようになりました。丘陵で暮らす人が市街地に出かけるには坂道を往復しなければなりません。1855年頃から丘の斜面に、ケーブルカーのような傾斜式エレベーターが盛んに作られるようになりました。アセンソールは電気を動力とすることなく、重力だけを利用して斜面を滑るように上下します。手軽で便利な乗り物が次々に作られ、多いときには30本近くのアセンソールが稼働していました。現在でも6本の現役で活躍し、住民の貴重な足となっています。


市街地の中心にあるビクトリア広場と南の丘を結ぶアンセソールは、エスピリトゥ・サントと呼ばれています。運行が始まったのは1911年9月13日のことです。ケーブルの長さは約40メートル、傾斜角度は45度前後で約30メートルの高低差を往復します。赤色と黄色に塗り分けられた客車はマッチ箱のようにも見えます。運行と同時にバルパライソのランドマークの一つに数えられました。


丘の上下に設けられた駅は何の飾り気もない素朴な小屋で、ノスタルジックな雰囲気を漂わせています。手作り感満載の壁や窓からは、温かさが滲み出てくるかのようです。斜面からはみ出す丘上の駅には、危うさと同時に微笑ましさが感じられます。



アンセソールで登った丘の上は異次元の空間です。土地の傾きなど一切気にせず、民家が埋め尽くしています。しかも家屋の壁面やトタン屋根はカラフルにペイントされています。思い思いの色彩で自宅を装飾することによって、丘の空間をアート作品に創りあげているかのようです。丘面を湾曲する階段や坂道からは、眼下にバルパライソの港をはじめバルパライソの市街地が広がります。


バルパライソは2003年に、バルパライソの海港都市と歴史的な町並みとして、ユネスコ世界遺産に登録されました。
【データ】
バルパライソのアンセソール・マップ:http://ascensoresvalparaiso.org/